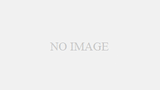乳幼児期のアタッチメント形成が、人間の生涯にわたる心身の健康や心理・社会的な発達に非常に重要な役割を果たしていることが最近の研究で明らかになってきています。
英国の児童精神科医、ボウルビィが1950年代にアタッチメント理論を提唱しました。
その理論の日本語訳で「アタッチメント」が「愛着」と訳されたのですが、アタッチメントの元来の意味は、付着する、つまり「くっつく」ということです。
たとえばヨチヨチ歩きの幼児が何かにつまずいて転んで、すごく痛かった。
子どもは当然、泣きながら助けを求めます。その声を聞いた母親が駆け寄って抱き上げ、ヨシヨシをします。子どもは安心して泣き止み、しばらくするとまた歩き始められる。
こんなふうに、怖いとき、不安なとき、困ったときに、特定の信頼できる誰かにくっつくことで、「ああ、もう大丈夫だ」と安心感に浸れる体験のことをアタッチメントといいます。
愛着というと「この車は長く乗ってきたので愛着がある」みたいに慣れ親しむという意味でとられたり、「家族はお互いに愛をもって接しましょう」といった親子間の愛情や関係性と考えられたりする場合もありますが、心理学でのアタッチメントとは意味が異なります。
養育者が子どもにスキンシップをして、愛情を持った関わりをするのはもちろん大切なことです。
でも、親子でいつもベタベタ密接しているというよりは、困ったらどんなときでも助けてもらえるという情緒的な絆が本質であり、アタッチメントとはつねに子どもが主体となる概念です。
体の発達は見えるのでわかりやすいですが、心の発達は目に見えません。
大切なことは、発達には必ず順序があるということです。
寝返りできない赤ちゃんがいきなり歩くことは不可能です。それと同様に、心の発達にも順番があります。心の発達の最初の課題は「他者への基本的信頼」です。
乳児期に、お腹がすいて泣けば養育者から授乳してもらえるといった、不快なことが快に変えられて満たされる体験を繰り返すことで、子どもの心に「自分は大切な存在だ」という自尊感情が芽生え、この世界や他者への信頼で、心が安定します。
それがいわば心の土台となるのです。心の土台、「大丈夫感覚」ともいいます。
養育者への信頼を十分に築けた児は、その養育者を安全基地として、遊びという探索行動を始めます。
安心感に満たされている児ほど、いざとなったらいつでも戻れる、保護してもらえることへの確かな見通しがあるので、より自発的な探索ができ、独りでも平気でいられるようになります。
でも、基地を離れると、予期せぬ事態に陥ったり、不安や恐怖が強くなったりすることも当然あります。そうなると、養育者という安全な避難所に戻ってきます。
そこで、安心感を再び獲得すると、また探索に出かけられます。
このような行動を繰り返しながら、心の発達の次なる課題の「自律性」や「積極性」、さらには「社会性」を徐々に獲得していくことができるわけです。
アタッチメントを形成するために非常に重要な感受期は2歳までといわれています。脳神経学的にも、この時期に過剰な神経細胞の刈り込みが起こり、神経回路のネットワークが確立されていきます。児が周囲へいくら要求しても的確な応答が得られないと、この刈り込みが十分に起こらずに、大脳での効率的な情報処理ができないまま、大きくなってしまう恐れがあります。
乳幼児のアタッチメントの形成のために、親の行動で大切なポイントは、①タイミング、②正確性、③一貫性の3点です。つまり、児が何か欲していることに、親が、①早く気づき、②正しく汲み取り、③一貫して同じことを繰り返す、ということです。
しかしながら、乳幼児の要求をつねに敏感にとらえ、正確に対応していくことは本当に至難の業です。
完璧に応えることはまず不可能です。できる限り、児の要望を理解して、応えてあげようと努力する時に、養育者も親として成長します。
また、アタッチメントは幼少期だけに必要かというと、そうではありません。大人になっても不安なことや困ったことは誰にでも起こります。心の安全基地となる特定の人へのアタッチメント関係は、生涯にわたってその人の人間関係のテンプレートのようになって、社会における対人関係、恋愛関係、夫婦関係などにも影響します。私もだいぶ本物のおじいちゃんになってきましたが、いまだに親愛なる家族、偉大な先輩、心から信頼できる友だちを中心にして、日常の人間関係を築いていると実感しています。
子育て中の母親にもそれは同じなのです。慣れない子育て、不安で一杯の母親にとって、子育てに協力する家族や援助者からの支援は不可欠です。小児科・産科などの医療施設や母子保健機関が母親の安全基地として果たす役割は非常に重要です。英国の児童精神科医、ウィニコットによる、「ただ一人の赤ちゃんというものはいない。そこに在るのは、赤ちゃんと養育者の関係性だけだ。抱っこされたいのは子どもだけではない。親もまた(心理的に)抱っこされたいのだ」という提言がそれを顕していると思います。